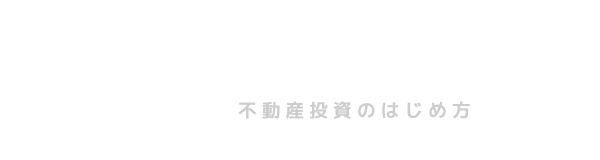日本における人生100年時代の所得問題
日本の所得代替率は低い

「所得代替率」とは、年金を受け取り始める時点(65歳)における所得額が、現役世代の所得額と比べた割合を示すものです。
| 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | OECD平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得代替率 (公的年金のみ) |
34.6% | 38.3% | 22.1% | 38.2% | 60.5% | 40.6% |
| 所得代替率 (DB・DC含む) |
57.7% | 71.3% | 52.2% | 50.9% | 60.5% | 58.7% |
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/market_wg/siryou/20190412/03.pdf
(人生100年時代における資産形成 金融庁)
日本の高齢者の資本所得の割合は低い
日本の高齢者の所得の内訳を見ると 、諸外国と比べ、労働所得の割合が高く、公的所得(公的年金)・資本所得(私的年金や非年金貯蓄としての収入)の割合が低いです。
の所得の内訳-1024x541.png)
日本の家計貯蓄率は低い
日本が貯蓄大国だったのは昔の話、いまは日本の家計貯蓄率OECD平均4.8%より低い状態です。
| 日本 | アメリカ | イギリス | ドイツ | フランス | OECD平均 | |
| 家計貯蓄率 | 2.6% | 6.9% | 1.6% | 9.8% | 8.2% | 4.8% |
(※)家計貯蓄率は、「家計貯蓄/家計可処分所得」。
日本は長寿化している

60歳の夫婦のいずれかが、少なくとも95歳まで生存する割合は5割弱と予想されています。
現役世代(特に30代・40代)の収入・貯蓄が減少している

1990年代以降、老後に備える現役世代のうち、50歳代の金融資産額が概ね横ばいである一方、いわゆる子育て世代に相当する30歳代、40歳代の家計において金融資産額、世帯収入がともに減少しています。

金融資産額が少ない高齢者世帯の割合が上昇している

高齢者夫婦のみ世帯の金融資産額の世帯数分布を見ると金融資産額3,000万円以上の世帯の割合が最も大きい。一方で金融資産額が少ない世帯(450万円未満)の割合が上昇し、二極化が進んでいます。


つまり我々は稼ぎ方・貯め方・増やし方を現役世代のうちに見直し、老後に備える必要があります。